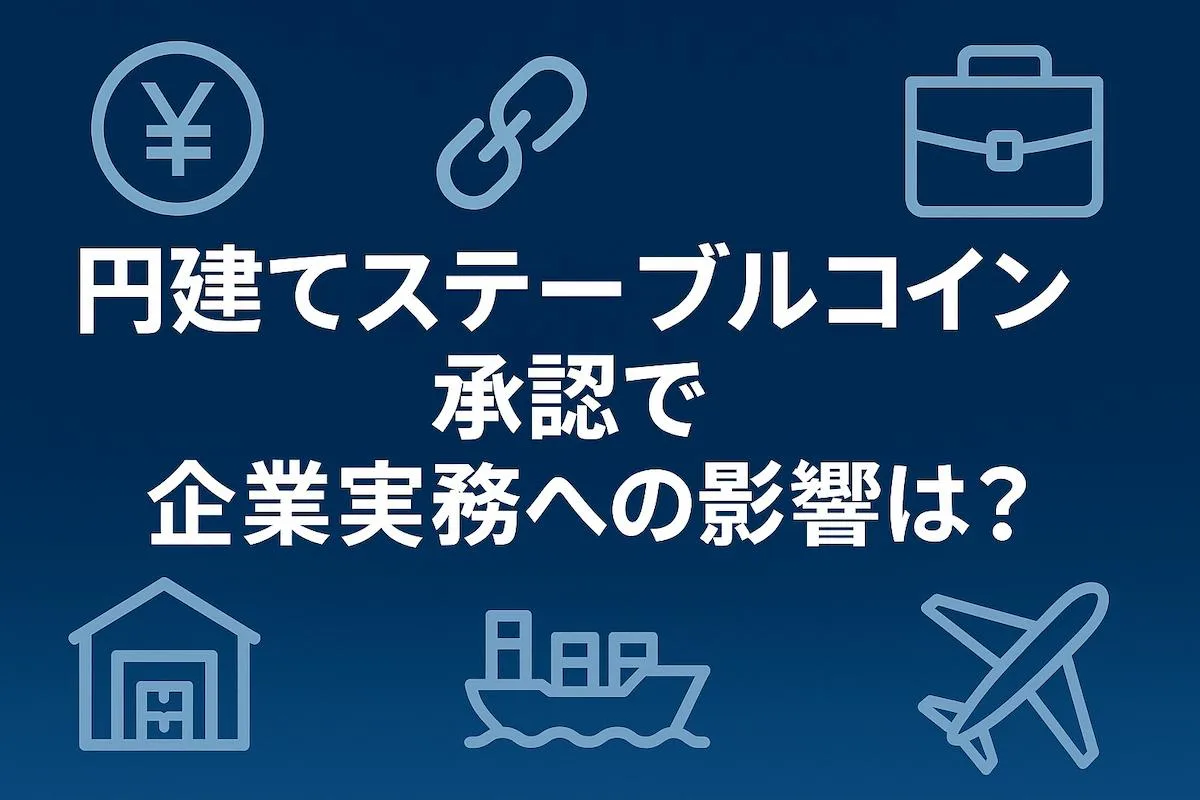2025年8月、金融庁が国内初となる円建てステーブルコイン「JPYC」を承認する方針が複数メディアで報じられ、発行は今秋見込みと伝えられています。
JPYC側トップも事実関係を認めた旨の取材記事が出ており、国内決済の転換点になり得るニュースです
NHKも「国内初 円建てステーブルコイン発行の見通し」として報じ、貿易等での活用可能性に言及しました。
さらにロイターは、裏付け資産(銀行預金や日本国債)の運用益を原資に発行・償還手数料ゼロを目指す設計や、秋の発行計画を伝えています。
今回は円建てのステーブルコインが登場することで企業実務への影響について考えてみたいと思います。
ステーブルコインとは?
まずは今回の話の前提となるステーブルコインについて解説していきましょう。
ステーブルコインの定義
ステーブルコインは円やドルなど法定通貨等に価値を連動させたデジタル通貨のこと。
資金移動業者は、ステーブルコイン発行残高と同額以上を供託金として保全することが義務付けられています。
そのため、理論上は発行したステーブルコインをいつでも全て法定通貨等に償還することが可能なため、安全性が高く価格の変動を抑えているんですよ。
日本では改正資金決済法で「電子決済手段」として位置づけられ、通常の暗号資産(ビットコイン等)とは別枠で規制されています。
ステーブルコイン 一覧
ちなみにステーブルコインは他にもあります。
| 名称 | 連動 | 発行主体/概要 | 日本での入手可否(例) |
|---|---|---|---|
| JPYC | 円 | JPYC株式会社。今秋発行見込み、裏付けは預金・JGB、手数料ゼロ方針報道 | 公式販売所(JPYC EX)から発行/償還開始見込み。交換業者経由の二次流通は今後 |
| USDC | 米ドル | Circle社。透明性・証明報告 | SBI VCトレードで国内初の一般向け取扱い(2025/3/26) |
| USDT | 米ドル | Tether社。世界最大規模 | 国内取引所での取り扱いなし(2025年時点) |
| CNHT | オフショア人民元(CNH) | Tether社が2019年に開始。現在はEthereum/Tron等で流通 | 国内交換業者での一般取扱い例は未確認 |
ポイント:国内での円建てステーブルコインはJPYCが初。ドル建てはUSDCが先行導入済み(SBI VC)。USDTは国内未対応。
ビットコインとの違い
暗号資産といえばビットコインが一番メジャーですが、それとはどう違うのでしょう?
大きく3つの違いがあります。
価格
ビットコインは需給で変動します。
一方、ステーブルコインは1円=1JPYCのようにペッグ(固定)を維持する設計です。
つまり、ビットコインのように価格が大きく変動するのを抑えているのです。
決済手段として使おうとすると価格が変動しまくるビットコインは使いにくいです。
その部分を改善したのがステーブルコインというわけです。
この点が一番違いますね。
発行主体
ビットコインは分散発行、ステーブルコインは登録事業者が発行し、裏付け資産を保有という違いもあります。
ステーブルコインの承認は国内でなかなか進まかなかったそうですが、国債を買うことになるという事がわかってから金融庁も乗り気だったという裏話も漏れ聞こえてきます。
用途
ビットコインは投資・価値保存色が強い一方、ステーブルコインは送金・決済の実務利用を想定。
同じ技術が基盤にはありますが、用途がかなり違う形ですね。
日本の法制度の要点(企業が押さえるべき前提)
それでは企業が国内初のステーブルコインにどのように対応すればよいのでしょう?
押さえておくべきポイントをみていきます。
法的位置づけ
2023年施行の改正資金決済法で、ステーブルコイン=電子決済手段とされました。
発行者(銀行/資金移動業/信託)と仲介者(電子決済手段等取引業者)の枠組みが整備されたのです。
会計面
企業会計基準委員会(ASBJ)は電子決済手段の会計処理の当面取扱いを公表。
監査・開示の論点は整備が進展しています。
当面の取り扱いですけどね笑
>>参考:資⾦決済法における特定の電⼦決済⼿段の会計処理及び開⽰に関する当⾯の取扱い
監督・登録の確認
取扱業者は金融庁/財務局の登録一覧で確認可能となっています。
おそらく詐欺も出てくるでしょうから実務運用では取り扱いをする前にここを台帳的に参照することが必要です。
>>参考:免許・許可・登録等を受けている事業者一覧
JPYCの仕組みと将来性
次にJPYCの仕組みと将来性についてみていきましょう。
裏付け資産
ステーブルコインは裏付け資産があり、価格の変動を抑えます。
銀行預金や日本国債など流動性の高い資産で1:1裏付けとのこと。
運用益で手数料無料方針(発行・償還)を狙う設計が報じられています。
※報道ベースでまだ不明の部分もあります。
発行計画
今秋発行開始見込みとのこと。
報道では3年で1兆円発行規模の目標言及も(現時点は計画段階の報)。
エコシステム
「JPYC Prepaid」(前払式支払手段)からの法対応として2025/6/1以降の新規発行終了を公式が発表。
今後は法定枠組みのJPYC(電子決済手段)が中核になりえるとしています。
JPYCはどこで買えるのか?
初期は公式の発行/償還サービス(JPYC EX)を通じ、銀行振込 ⇄ ウォレット送付の流れが想定されています(秋の開始見込み)。
発行・償還手数料は無料方針(別途ガス代等)との解説記事も。
最新は公式と登録一覧で確認ください。
将来性
即時性・低コスト・プログラマビリティ(自動化)は、資金繰り・回収・越境ビジネスの合理化に直結しそうです。
特に海外との取引が多い企業にはかなりプラスになりそうな予感。
法整備と会計・監査の整備が進み方次第によっては日本市場でも、企業導入の障壁が下がりやすい環境となりえます。
企業への実務インパクト(メリット/注意点)
それでは企業から見たときにどのような影響があるのかを詳しく見ていきましょう。
メリット
まずはメリットです。
入金即時化とコスト最適化
銀行営業外の夜間・休日でも即時着金。
裏付資産の信頼性と手数料ゼロ方針(ガス代等は別)が報じられており、少額・高頻度決済にもありがたい存在となりそうです。
逆にいえば銀行のビジネスも大きな転換期を迎えそうな予感・・・
越境取引の円建て化
円建てのまま送金・決済が可能となります。
海外ステーブルコインに依存しない対外決済レールの選択肢拡大しそうです。
自動化(スマートコントラクト)
デリバリー連動の自動支払(エスクロー的)、サブスク課金、マイル/ポイント連動など業務のDXをさらに加速化させそうです。
注意点(リスク)
次に注意点(リスク)です。
発行・償還フロー
取扱は登録業者経由が原則です。
社内KYCフローや受取ウォレットの管理権限を明確化が必要となります。
今後は登録業者の与信部分などが課題になってきそうな予感もあります。
会計・監査
電子決済手段の会計・開示に準拠(ASBJ/監査実務が整備中)。
評価・表示区分、キャッシュ・フロー計上など、監査人、税理士と事前合意をしておく必要がありそう。
この分野に長けた会計人も多くはなさそうなので当面はネックとなりそう。
社内統制とカストディ
秘密鍵管理・承認権限・多重署名等の内部統制が必須。
外部カストディの是非も検討が必要かもしれません。
人件費・賃金支払い
給与のデジタル払い制度は別途要件があります。
賃金は原則現金(法定通貨)が原則で、ステーブルコインが制度に適合しているのかの確認が必要となります。
中小企業にとっての使い道
ステーブルコインというと大手企業だけの話でしょ?
中小企業には関係ないと思っている方も多いと思います。
しかし、逆なんですよ。
中小企業こそ使うべきものとなりそうなのです。
事例を見ておきましょう。
B2B決済(卸・仕入・外注費)
入金が即時で手数料も少ないので下請け/協力会社の資金繰りを改善に寄与します。
また、納品検収トリガー→即時支払のスマコン化も可能です。
EC/サブスク(D2C/会費)
返金(償還)・継続課金の自動化も可能。
入金照合も容易で、債権管理/消込工数を削減に繋がります。
越境取引(輸出入)
円のまま短時間・低コストで国境を越える決済レールです。
為替リスクや銀行休業日の影響を緩和に繋がりますね。
これで越境EC等の海外ビジネスの敷居が低くなります。
導入ステップ(実務チェックリスト)
それでは実際に導入するとなればどのような点を確認する必要があるのでしょう。
チェックリスト式にみていきましょう。
Step 1:社内方針と目的定義
- 何を改善したいかを考えましょう。
たとえば入金サイクル短縮/越境コスト/決済自動化などです。
Step 2:業者・ウォレット選定
- 登録済みの取引業者かを確認は必須
- カストディ(自己保管/外部委託)を決定。
Step 3:会計・監査同意
- ASBJの当面取扱いに沿った勘定科目・時点認識・開示方針を監査人と握る。
Step 4:内部統制/権限設計
- 多重承認、秘密鍵/復元フレーズ管理、送金先ホワイトリスト、監査証憑のログ化。
Step 5:運用テスト(PoC)
- まずは少額・社内間取引で回し、入出金・消込・税務の一連を通しで検証。
Step 6:対外展開・規約整備
- 取引基本契約・約款・個人情報/AML規程の改訂、返品・償還ポリシーの明記。
まとめ
今回は「国内初の円建てステーブルコインJPYCが承認へ:企業実務への影響と導入手順|ビットコインとの違いも解説」と題して円建てステーブルコインJPYCが承認されるという話を見てきました。
まだ秋に承認と少し先の話ですが、情報収集と導入の準備をすすめておきたいところ。
越境・B2B・ECで即時性/自動化の恩恵が見込め、中小企業の資金繰り・業務効率化に直結する可能性があります。
ただし、会計面やセキュリティ面などまだ不安な部分もあります。
まずは少額からの段階導入が現実的ですかね。